専門研修プログラム
専門研修プログラムとは
専門研修プログラムとは専門医を育成する研修コースです。
3年間の研修を通して、知識・技能・リーダーシップを修得していきます。
専門研修プログラム期間中の研修医を専攻医と呼びます。
概要
2年間の初期臨床研修後、3年間の専門研修(後期研修)で
リハビリテーション科専門医取得を目指します。
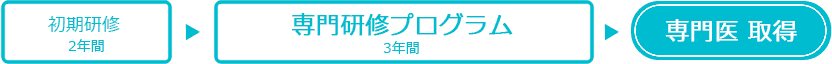

研修プログラムで経験すべき症例数は日本リハビリテーション医学会専門医制度により定められています。
専門医を取得するには100例以上の経験症例が必要です。
また、8つのリハビリテーション領域をまんべんなく経験するように研修カリキュラムに示されています。
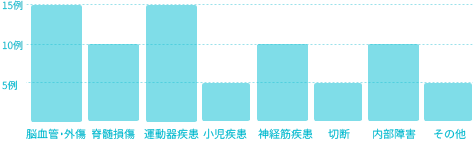
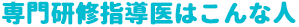
- リハビリテーション科の専門医です。
- リハビリの診療・教育・研究に長く携わっています。
- 学会で主演者として口演し、論文を発表しています。
指導医は、教育の中心的役割を果たすとともに、指導した研修医を評価します。
また、研修医からも、指導法や態度について評価を受けます。
3年間のながれ
1年目
リハビリテーション科の基本的知識と技能の概略を理解し、
できるところから実践していきます。
指導医の助言・指導の下に、基本的診療能力を身につける期間です。

2年目
指導医のもと、修得するべき診断・検査・治療の大部分を実践します。
診療能力の向上に加えて、コメディカルへの指導も担ってく期間です。
連携施設での勤務を通して、経験症例の幅を広げていきます。

3年目
指導医の助言から独立して、チーム医療の中心的な役割を果たす期間です。
迅速かつ状況に応じた対応が求められ、他の診療科との連携も担っていきます。
症例に特徴がある連携施設での勤務を経験し、各リハビリ分野を網羅する知識を習得します。

勤務する連携施設は相談の上決定します。
勤務期間は各施設に設けられている期間の間で、研修医の希望に応じて設定します。
研修施設
北海道大学病院を基幹病院とし、札幌市を中心とする6施設から研修先を選択することができます。
研修施設群にはリハビリテーション専門病院、小児専門施設、高齢者専門施設、地域中核病院が入っています。
| 脳 | 脊 | 運 | 小 | 神 | 切 | 内 | 他 | |
| 北海道大学病院 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
| 市立函館病院 | × | × | ● | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 北海道立 子ども総合医療・療育センター | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × |
| 苫小牧東病院 | ○ | △ | ○ | × | △ | × | × | ○ |
| 花川病院 | ○ | × | ○ | × | × | × | △ | ○ |
| 日鋼記念病院 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独立行政法人 国立病院機構北海道医療センター | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ○ |
| 札幌秀友会病院 | ○ | × | ○ | × | △ | × | × | △ |
| ●500以上 ◎100以上 ○10以上 △1以上 ×症例なし | ||||||||
|
| |||||||
経験症例数
専門研修プログラムでは、必須経験症例数が定められています。
経験できる症例の傾向は研修施設ごとに異なっているので、
プログラム全体を通して不足なく症例を経験できるよう確認しておきましょう。
経験すべき症例数
| 脳血管障害・外傷性脳損傷など | 15 |
|---|---|
| 脳血管障害 | 13 |
| 外傷性脳損傷 | 2 |
| 脊椎脊髄疾患・脊髄損傷 | 3 |
| 運動器疾患・外傷 | 22 |
| 関節リウマチ | 2 |
| 肩関節周囲炎、腱板断裂などの肩関節疾患 | 2 |
| 変形性関節症(下肢) | 2 |
| 骨折 | 2 |
| 骨粗鬆症 | 1 |
| 腰痛・脊椎疾患 | 2 |
| 小児疾患 | 5 |
| 脳性麻痺 | 2 |
| 神経筋疾患 | 10 |
|---|---|
| パーキンソン病 | 2 |
| 切断 | 3 |
| 内部障害 | 10 |
| 呼吸器疾患 | 2 |
| 心・大血管疾患 | 2 |
| 末梢血管疾患 | 1 |
| その他の内部障害 | 2 |
| その他 | 7 |
| 廃用症候群 | 2 |
| がん | 1 |
基幹病院
施設概要
(急性期)病床数20床
専攻医経験予定症例数(年間)
摂食嚥下訓練225例 ブロック療法135例
目次
連絡先
011-706-6066 (研修担当者 千葉 春子)
rehabilitation@huhp.hokudai.ac.jp